高校受験に合格するために通う塾ですが、塾に通うタイミングを間違えてしまうと、中学3年生の冬に「志望校に行けなかった!」という悲しい結果になってしまうかも・・・。
塾講師歴10年の経験を持つユー・スリーが、いつから塾に通うとベストなタイミングなのかを具体的な時期でご紹介します!

お子さんが塾へ入るタイミングで悩まれている親御さん達の参考にしていただけると光栄です。
元塾講師がおすすめ!塾に通うタイミングBEST3

 小学6年生3月(中学1年入学前)
小学6年生3月(中学1年入学前)
塾に行くタイミングの第一候補は、中学英語を入学前から学習する小学6年生3月(中学1年入学前)です。
なぜなら、中学の教科と小学校の教科で決定的に違うのが、「英語」だからです。
小学校でも英語は必修化されていますが、中学校の英語は高校受験で必須科目のため、重要度が小学英語の比ではありません。
小学校英語を「のび太くん」とすると、中学英語は「ジャイアン」と言っていいぐらいの差があります。
小学6年生の3月の塾では、アルファベットやThis is a pen.といった簡単な基礎英語を先取り学習します。
中学校へ入学するまでの1ヶ月間、ゆっくりと中学英語を学習できるので、4月から始まる中学英語に何も心配なく入っていけます。
英語に対する苦手意識を持たずに、中学英語を始められるタイミングが小学6年生3月(中学1年入学前)です。
 中学1年生5月後半~6月頃(中間テスト終了後)
中学1年生5月後半~6月頃(中間テスト終了後)
入塾タイミングの第二候補は、人生初めての定期試験が終わった中学1年生5月後半~6月頃です。
実際に中学校の定期試験を受けるまでは、自分の学力がどの程度なのか分からりません。
「そんなに急いで塾に入らなくてもいいの!」
「自分でやってみるから、心配しないで。」
「小学校の時に英語も習ったから、余裕www」
中学入学前に塾に通わないお子さんの言い訳は、自分の学力が全体の中でどの位置にいるのか分かってないことが原因です。
中学生になって初めての1学期中間試験後に自分の学力の位置を知り、高校入試や今後の勉強に対して不安感が出てきます。
繰り返しになりますが、英語は中学生になって全員が横一列でスタートする教科です。
3月から学習をスタートして全力で走り続けているグループと、4月から遅れてスタートしてマイペースで走っているグループに大きな差が出てしまうのは明らかです。
遅れと言っても、まだまだ余裕で挽回できるタイミングが中学1年生5月(中間テスト終了後)です。
入塾後、ペースの速いお子さんの場合、早ければ1学期後半の期末試験から結果が出ます。
遅くとも夏休みの夏期講習で行われる1学期の復習と2学期の先取り学習で、2学期の中間試験からは先行グループに追いつけます。
 中学2年生7月(1学期期末試験終了後)
中学2年生7月(1学期期末試験終了後)
入塾タイミングの第三候補は、高校入試から逆算してギリギリ間に合う中学2年生7月です。
中学2年生の2学期からは、1年生全範囲と2年生1学期の内容を基礎として難易度と学習量がグッと上がります。
中学2年の2学期から遅くなればなるほど、苦手科目の挽回が難しくなっていきます。
特に、英語・数学の難易度が上がり、社会は地理・歴史と2分野の学習、理科は数学のような計算が必要となり、ますます学習時間が必要になる時期です。
各教科が難しくなる中学2年2学期に備えて、入塾をするタイミングが中学2年生7月です。
7月に塾に通えると夏休みの夏期講習を受講できますし、友達がどのくらい勉強に時間を割いているのかも分かります。
さらに、夏休み中の塾で強制的に学習習慣が身についていきます。
2年生の夏休みから友達同士で志望校の話をし始めるため、高校入試に向けた意識付けにも役立ちます。

塾に行かせるおすすめなタイミングは分かったけど、うちの子供は志望校が決まってないのよ。

本人が高望みはしていないのに、中1から塾に通う必要ある?

次は志望校が「ある」「なし」の2パターンに分けて、塾に通うタイミングをご紹介します。
塾に通うタイミングは、志望校のレベルで決まる

塾に通うタイミングを計るもう1つの方法は、志望校のレベルから逆算する方法です。
指標として活用しやすい中学校の定期テストの得点から塾に入るタイミングを考えてみました。
内申点にカウントされる通知表の判断指標となる定期テストは、中間試験+期末試験の平均点が60点前後となるように作成されています。
定期テストは、得点を見れば学年でのおおよその学力順位が分かるため、志望校を決めるための最重要テストの1つです。
志望校が決まっている場合
志望校が決まっている場合は、学校の面談等で同じ中学から志望校に進学した卒業生の得点を確認しておきましょう。
合格者の得点に足りない場合は、すぐに塾に通うことを検討できますし、十分に得点を満たしているなら塾に通う必要さえなくなります。
さらに、定期テストで必要となる得点が分かれば、目標設定ができ今後の勉強のペースも把握できます。
志望校に必要な得点 定期テスト300点「平均レベル」
 志望校に必要な得点が300点前後の場合、余裕を持って塾に入るタイミングを検討できます。
志望校に必要な得点が300点前後の場合、余裕を持って塾に入るタイミングを検討できます。
学校の定期テストは、中間+期末試験合わせて平均60点程度となるように作成されています。
5教科で合計300点であれば、5科目全て平均レベルが取れていれば問題ありません。
志望校の偏差値も45~55となるため、中学1年生~中学2年生秋前まで塾に通わなくても志望校に合格できる可能性があります。
ただし、中間テスト+期末テストで2回連続300点以下になった場合は、時期に関係なく塾の利用をおすすめします。
志望校に必要な得点 定期テスト350点「上位レベル」
 志望校に必要な得点が350点の場合、平均以上の学力が求められます。
志望校に必要な得点が350点の場合、平均以上の学力が求められます。
志望校の偏差値55~63となり、選択できる高校の数が最も多くなるゾーンです。
英語・数学の得点率が合否に大きく関わってくるため、英語・数学は塾に通いながらコツコツと学力をつけていきたい教科です。
英語・数学を苦手科目にしてしまうと第1志望校を変更することになるので、定期テストの英語・数学の得点には気をつけてください。
英語が平均点以下しか取れない場合は、直ぐにでも対策をとらないと手遅れになってしまいます。
英語の得点を判断基準とすると、中学1年生の冬休み~ギリギリ中学2年生の夏休み前までに、塾へ通われることをおすすめします。
定期テスト400点以上 最上位レベル
 志望校に必要な得点が400点以上の場合、クラスでTOP3・学年でTOP15以内の学力が必要です。
志望校に必要な得点が400点以上の場合、クラスでTOP3・学年でTOP15以内の学力が必要です。
合計400点以上つまり5科目平均80点以上という高いハードルとなり、なかなか自学自習だけでは到達できません。
塾を利用しながら最短距離で勉強を進めていくと、学習面でお子さんの負担も減りますし、クラブ活動にも時間を使える余裕が生まれてきます。
志望校の偏差値60~70の最上位レベルでは、高校入試の合格ラインが高得点帯となることが多く、塾に通っている生徒さんがほとんどです。
また、中学入試経験者が高校編入を目指して再度チャレンジしてくる高校もあります。
中学入試経験者は学習練度が高い生徒さんばかりなので附属中学がある高校は、ますます合格難易度が上がる傾向があります。
レベルの高いライバルに負けないために、小学6年生3月(中学1年生入学前)から塾へ通われることをおすすめします。
志望校が決まっていない場合
志望校が決まっていない場合は、定期テストの得点を参考にしながら、塾に通うタイミングを考えます。
偏差値53以上の高校を志望校とする場合、ざっくりですが中間テスト+期末テストの5教科合計平均点300点をボーダーラインと見てください。
定期テスト5教科合計300点以下は、学年全体で平均以下となります。
平均以下の成績を続けると、偏差値53以上の高校合格が非常に厳しくなるため塾通いのタイミングを見誤らないようにしてあげてください。
英語・数学のテスト結果で判断
5教科合計300点がボーダーラインとお話ししましたが、2科目「英語」「数学」は個別に見ておく必要があります。
例えば300点以下であっても、科目別の得点によって塾に入るタイミングが違ってきます。
| Aさん | Bくん | |
| 英語 | 80 | 50 |
| 数学 | 70 | 40 |
| 理科 | 50 | 80 |
| 社会 | 40 | 80 |
| 国語 | 40 | 40 |
| 合計 | 280 | 290 |
合計得点では「Bくん」がAさんよりも+10点獲得しています。
しかし、実際はAさんの方が伸びしろがあります。
なぜならAさんは、主要2科目である「英語」「数学」で平均点以上を獲得しているからです。
「理科」「社会」は、演習良を増やせば短期に得点を伸ばしやすい科目です。
一方、「英語」「数学」は積み重ねが必要な科目のため短期で得点を伸ばしずらい科目です。
「英語」「数学」で平均点以上を獲得しているAさんが塾に通い勉強時間を増やせば、350点をすぐに越えてくる可能性が高くなります。
「英語」「数学」を苦手としているBくんは、英語・数学2科目の対策が必要となるため塾に通ってもスグに結果が出にくいタイプです。
つまり、Aさんは塾に通うタイミングを遅らせることができますが、Bくんは早めに塾へ通う方が良いということになります。
英語が難しくなっている
2020年に中学校の教科書改訂がありました。
教科書の内容を見て驚いたのが、中学1年生の英語です。
塾講師をしていた当時の教科書と比べると倍以上難しくなっている印象を受けました。
教科書に出てくる単語の量・質が中学3年生レベル?と思ってしまうほどです。
今回の教科書改訂は、中学1年生の教科書だけ難易度が上がりすぎです。
中学1年生で英語が分からなくなった時は、英語1科目だけでも塾に通って苦手意識を持たないようにしてあげてください。
中学1年生の冬休みが分かれ目
中学生になって1学期、2学期で合計4回の定期試験を終えた冬休みが、勉強の出来るグループと苦手なグループに分かれていく境界線になります。
中学1年生の2学期までは、学力面に大きな差はほぼ出ません。
しかし、1年生の3学期、2年生の1学期と進むにつれてジワジワと学力差が広がっていきます。
というのは、1年生の3学期から学習内容が難しくなり、スピードも上がるためです。
志望校が決まっていないのであれば、1年生の冬休み(冬期講習)から塾に通うことをすすめします。
学習の量とスピードが上がる直前の1年生の冬休みから塾で先取り学習をやっておけば、急に成績が落ちたり勉強が苦手になってしまう事態を予防できます。

塾に通うタイミングは、主要2科目の「英語」「数学」がポイントなんですね。

志望校のレベルから逆算して塾に通うタイミングを考えるのは、知らなかったです。

ただ・・・お金のかかる塾に通うメリットって、本当にあるのでしょうか?

はい。授業をYoutubeで無料で見られる時代でも、塾に通うメリットはあります。
塾に通うメリット
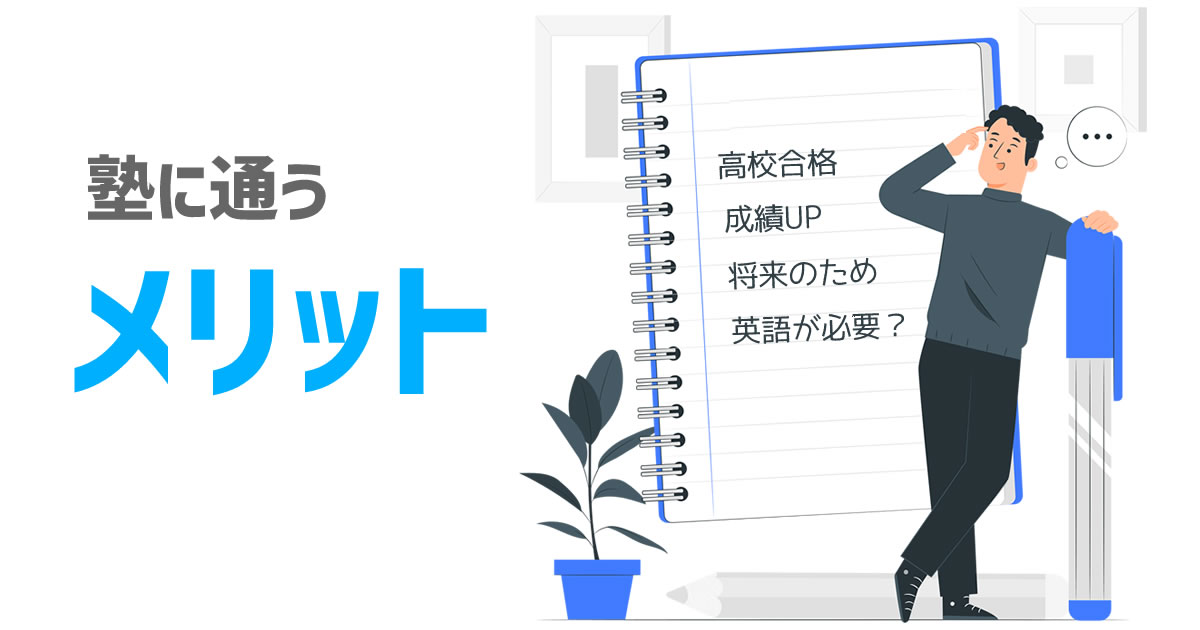 Youtubeなどで無料授業を見られるようになり、塾に通う必要がなくなってきたという話を耳にすることがあります。
Youtubeなどで無料授業を見られるようになり、塾に通う必要がなくなってきたという話を耳にすることがあります。
確かに、無料で配信されている授業と塾での授業に大きな差はないと思います。
しかし、映像授業を見ただけで本当に授業の重要ポイントが分かっているのかは判断できません。
料理のレシピ動画を見て作ってみたけど、映像の中のお料理のように上手く作れなかった経験はありませんか?
無料動画授業も、全く同じです!!
Youtubeの無料動画が持っていないメリットを、塾に通うことで享受できます。
授業の要点を繰り返し確認できる
塾に通うメリットの1つ目は、「リアルタイムで授業の要点を確認できる」ことです。
塾では授業の要点確認、演習問題の解説の順番で授業が進められていきます。
各授業には、理解して欲しい要点があり、要点確認、演習問題の解説、間違い直し、宿題で繰り返し要点確認が行われます。
何度も何度も繰り返すことで、要点を理解出来るように授業を構成しています。
特に、演習問題の回答中や、間違い直しの際にヒントとなる声かけで要点を思い出させるように誘導していきます。
私が講師をしている時は、講師が教えるのではなく、生徒本人が気づけた形に持っていくように考えていました。
成績アップするためのスケジュール
独学で中学校の5教科を勉強することが大変なのは、スケジュールを立てられないからです。
塾講師は受験のプロです。
中学3年間全体から、単元同士のつながり、最低限押さえておくポイントを完全に理解して授業を行っています。
初めて習うことで精一杯の中学1年生が、中学3年生で習うことをイメージして勉強することは不可能です。
まさに、「木を見て森を見ず」で勉強を進めるのが独学。
「空から全体を見渡して、確実にゴールへ進める」のが、塾での勉強です。
塾に通うメリット2つ目は、「最短で成績アップするためのスケジュール(地図)を手に入れることができる」ことです。
勉強仲間や勉強に集中できる環境がある
クラブ活動と同じように、勉強でも仲間の存在は欠かせません。
定期テストの得点で競ったり、分からないところを教え合ったりと、高校合格という同じ目標にに向かう仲間がいるからこそ、頑張れる時があります。
塾の授業は学校とは違い無駄話は一切無く、生徒さん達の集中度が格段に上がります。
教室全体が勉強を頑張る雰囲気のため、「塾の方が自宅より勉強できる!」と言う生徒さんもたくさんいました。
独りで勉強に集中しずらいお子さんであれば、塾の友達と一緒に勉強すると自分で驚くほど勉強に集中できた感覚を感じてもらえます。
塾に通うメリット3つ目は、「勉強仲間や勉強に集中できる環境がある」ことです。
塾に、いつから行けば間に合う?まとめ

塾にいつから通うのか?の答えは、「1日でも早くがおすすめ」です。
お子さんの学習状況、学力、クラブ活動への参加などの他、志望校のレベルも関係します。
もし今、迷われているなら「1日でも早く塾に通う」をおすすめします。
塾は、勉強の内容だけではなく高校入試までの最短の道筋を教えてくれます。
同じ宝(高校合格)を探しているなら、宝のありかを記した地図を手に入れた人が有利になります。
中学2年生の夏休み前をラインとして、塾へ通うのかどうかを慎重にご検討ください。



